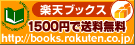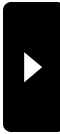青が散る
「青が散る」 宮本輝 文春文庫
書評(私見):




( :5個が満点)
:5個が満点)
心にのこるあの台詞:
「若者は自由でなくてはいけないが、もうひとつ潔癖でなくてはいけない。
自由と潔癖こそ、青春の特権ではないか」
(青が散る より)
書評(私見):





(
 :5個が満点)
:5個が満点)心にのこるあの台詞:
「若者は自由でなくてはいけないが、もうひとつ潔癖でなくてはいけない。
自由と潔癖こそ、青春の特権ではないか」
(青が散る より)
仕事ができる人できない人―「いい人」は無能の代名詞である!」
「仕事ができる人できない人―「いい人」は無能の代名詞である! 」 堀場雅夫 三笠書房
書評(私見):

( :5個が満点)
:5個が満点)
著者が仕事ができる人なのか、できない人なのかよくわからないけれども・・・。
この本は、自社の社員のタイプを一人ひとり例としてあげて語っていく内容。
しかし、イマヒトツ納得がいかない。きっと例示が具体適するのだと思う。
例えば、「石橋を叩いて渡るタイプの人」・・・確かに具定例だけ見れば
なるほどと思うのだけれども、それがすべてでいいのだろうか?
きっと会社という組織では、「石橋を叩いて渡るタイプの人」と「猪突猛進タイプの人」と、
その両方のタイプが必要なのではないだろうか?
いろんなタイプがいるからこそ組織としての力を発揮できるのだと、私は思うわけで・・・。
読破した後の感想としては、「この会社にはいろんな人がいるんだなぁ~。」といった感じです。
書評(私見):


(
 :5個が満点)
:5個が満点)著者が仕事ができる人なのか、できない人なのかよくわからないけれども・・・。
この本は、自社の社員のタイプを一人ひとり例としてあげて語っていく内容。
しかし、イマヒトツ納得がいかない。きっと例示が具体適するのだと思う。
例えば、「石橋を叩いて渡るタイプの人」・・・確かに具定例だけ見れば
なるほどと思うのだけれども、それがすべてでいいのだろうか?
きっと会社という組織では、「石橋を叩いて渡るタイプの人」と「猪突猛進タイプの人」と、
その両方のタイプが必要なのではないだろうか?
いろんなタイプがいるからこそ組織としての力を発揮できるのだと、私は思うわけで・・・。
読破した後の感想としては、「この会社にはいろんな人がいるんだなぁ~。」といった感じです。
オレンジの壺・下
「オレンジの壺・下」 宮本輝 講談社文庫
書評(私見):

( :5個が満点)
:5個が満点)
心にのこるあの台詞:
「人間の行動には、理に叶っていないことがたくさんあるみたいだが、
よく考えてみると、すべては理に叶ってるんだ」
(オレンジの壺・下 より)
書評(私見):


(
 :5個が満点)
:5個が満点)心にのこるあの台詞:
「人間の行動には、理に叶っていないことがたくさんあるみたいだが、
よく考えてみると、すべては理に叶ってるんだ」
(オレンジの壺・下 より)
朝の歓び・上
「朝の歓び・上」 宮本輝 講談社文庫
書評(私見):


( :5個が満点)
:5個が満点)
心にのこるあの台詞:
「だって、愛情ってのは、自然に、だんだんと育っていくものだからね。
それも一ヶ月や二ヶ月で育つもんじゃないさ」
(朝の歓び・上 より)
書評(私見):



(
 :5個が満点)
:5個が満点)心にのこるあの台詞:
「だって、愛情ってのは、自然に、だんだんと育っていくものだからね。
それも一ヶ月や二ヶ月で育つもんじゃないさ」
(朝の歓び・上 より)